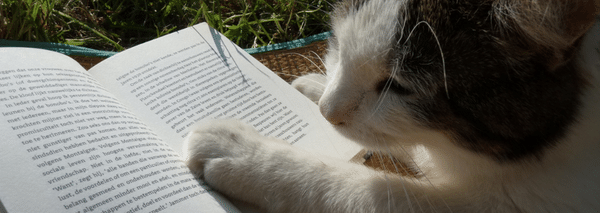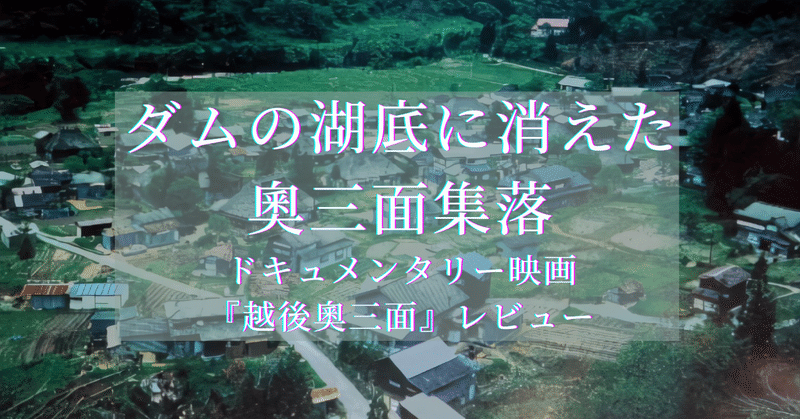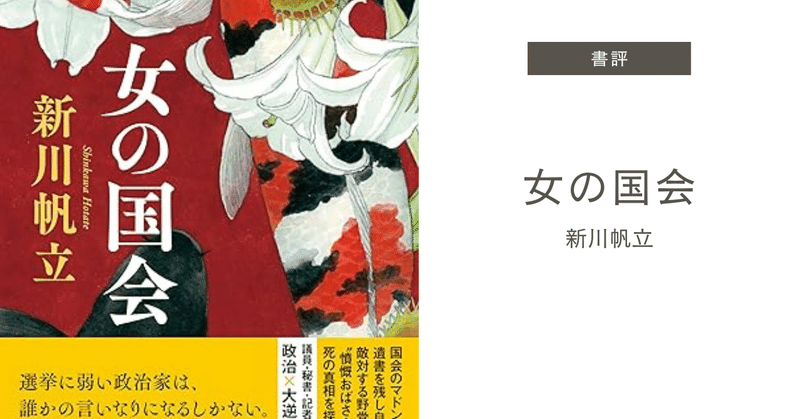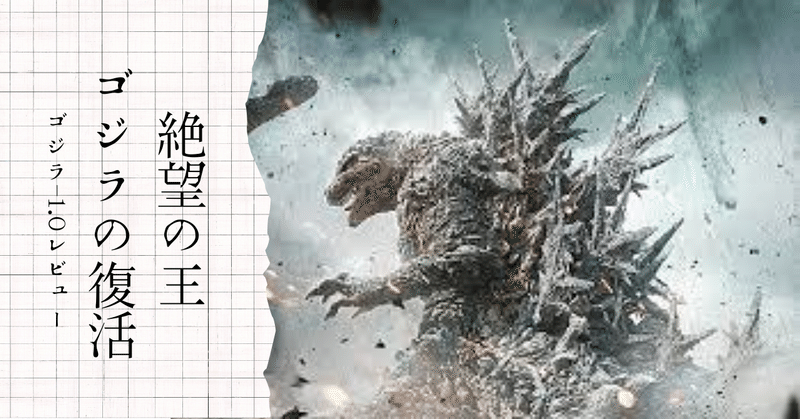サイエンスとプラグマティズムの間で
実験家・プラグマティスト。思考実験や社会実験を繰り返しながら、実用に向けた試行錯誤を実際の体験として積み重ねることが好きです。呟きは主にThreadsで @taishibrian お問合せ⇒https://note.com/taishibrian/message
人と猫の幸せな関係
「猫と働く、猫と暮らす」をコンセプトに建設した、SANCHACOのことについて主に語っています。 世田谷区三軒茶屋にある、保護猫の譲渡を進める賃貸住宅 / 猫が邪魔するワークスペース / 店舗利用できるレンタルスペースの複合施設SANCHACOでは、猫という存在をシェアしています。その可愛らしさや責任をコミュニティで共有していくことで、都市型ライフスタイルをもっと豊かにしていくことを目指しています。